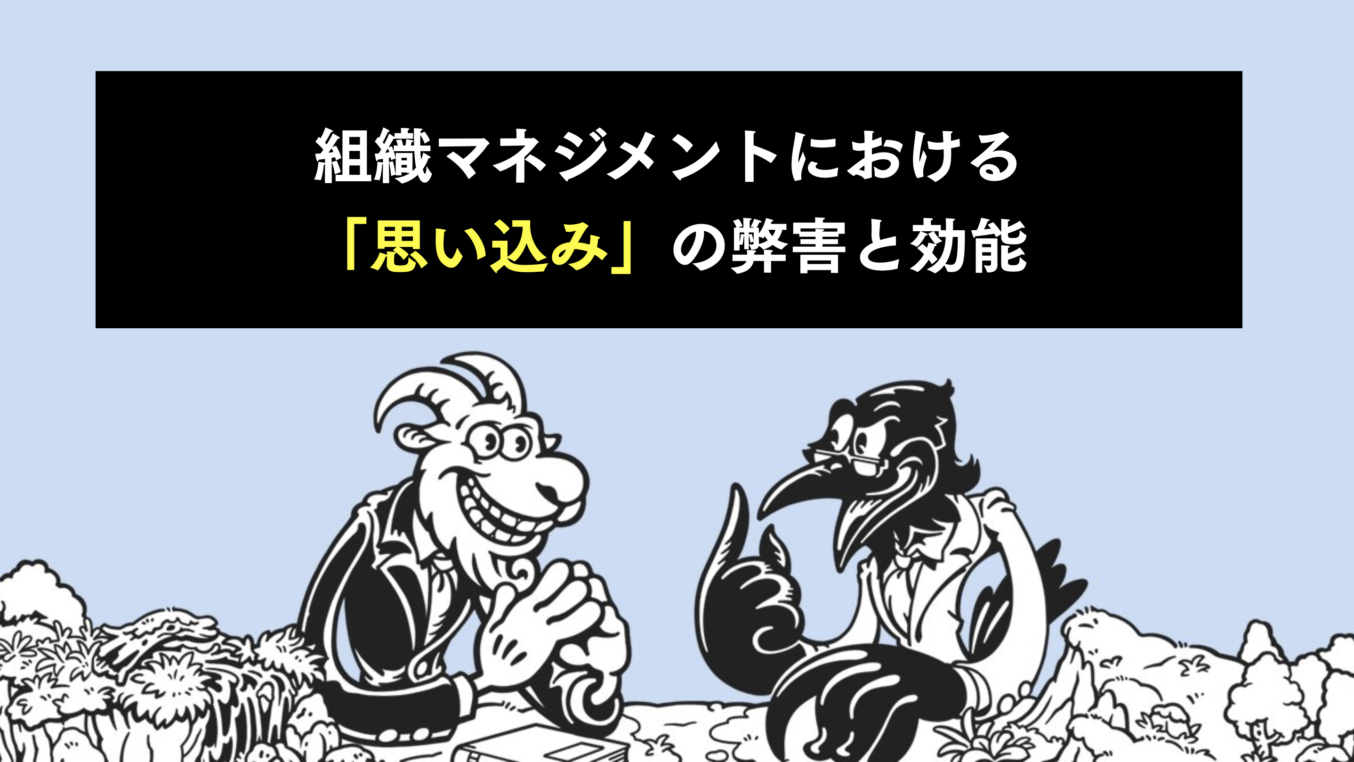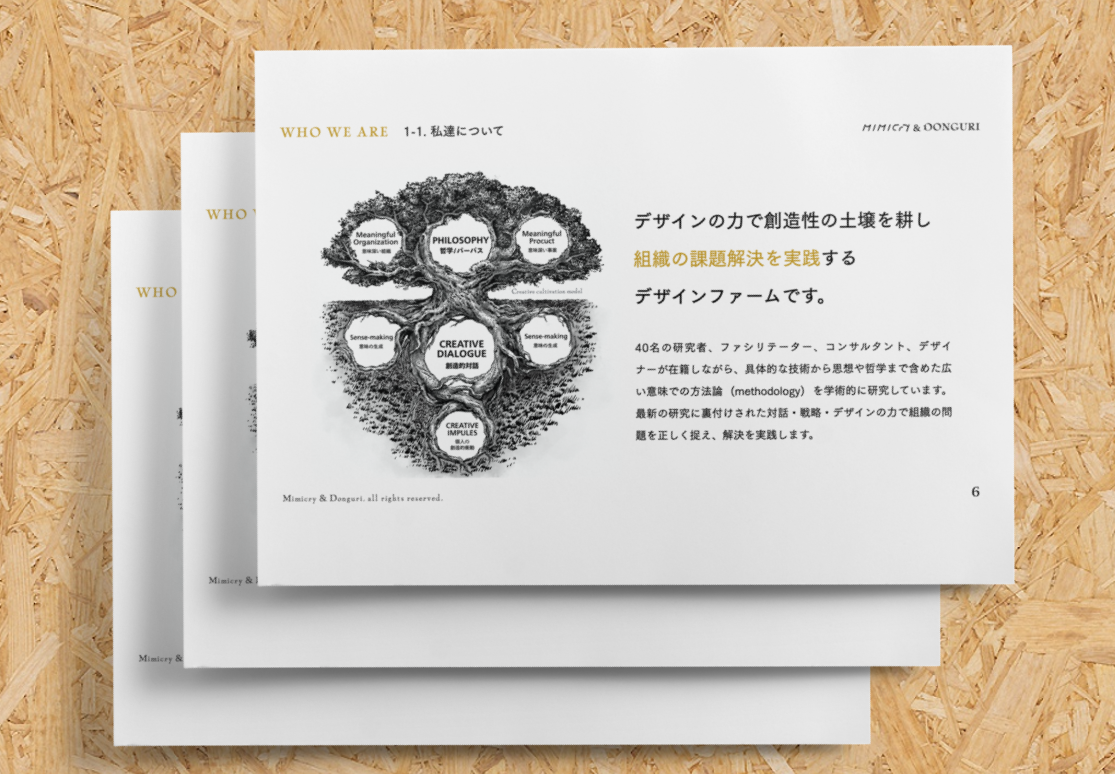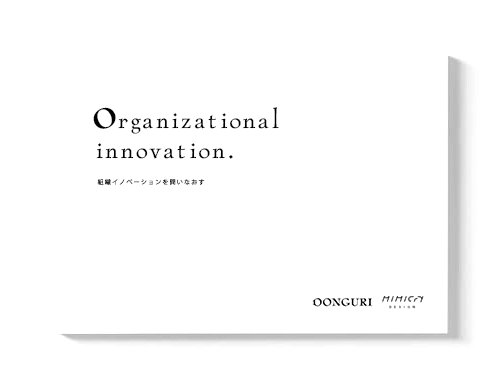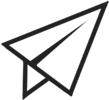今年の3月に『組織論と行動科学から見た 人と組織のマネジメントバイアス』という書籍が出版され、話題になっています。
驚くほど現場のマネジメントに参照されていない「学術研究」の知見
著者の一人である伊達洋駆さんは経営学者の金井壽宏先生のもとで博士課程に在籍されていて、安斎も大学院生の頃から研究や実践において長くお付き合いさせていただいています。伊達さんの先輩である服部泰宏先生に取りまとめていただきながら、2013年に『経営学者と実践家との関係性の再考』という研究報告を組織学会にてさせていただいたことがあるのですが、当時から一貫して「研究と実践をどのように接続させるか」ということが私たちの共通するテーマになっています。
経営学者と実践家との関係性の再考
服部泰宏,伊達洋駆,福澤光啓,舘野泰一,安斎勇樹 (2013)
2013年度組織学会研究発表大会報告要旨集,組織学会,pp53-56
本書の焦点もまたそこにあり、「組織マネジメントの実務において、研究知見や理論が正しく参照されていない」ことを問題意識として掲げながら、現場に蔓延している「バイアス(偏り・思い込み)」について、学術研究のエビデンスを示しながら批判的に検討し、正しく考えるためのヒントが提供されています。
マネジメントは「思い込み」に囚われてはいけない!?
たとえば、「カルチャーフィットを重視した採用は、業績向上につながる」「多面(360度)評価は、上司の単独評価よりも精度が高い」などの、採用、育成、評価などに関するバイアスが、次々に揺さぶられていく構成は痛快です。
他方で、上司が部下の学習能力を強く信じ込んでいるほうが、実際に育成効果があがる研究結果(固定理論)や、ダイバーシティの重要性を信じ込んでいるほうが、実際にダイバーシティによるパフォーマンス向上が高まる研究結果などが紹介されており、偏った思い込みが組織のポテンシャルを引き出す場合があることも語られます。
バイアスとは、いわば、少ない具体的経験から抽象的法則を導くヒトの経験学習能力の結果だと言えるでしょう。その経験による法則が、研究知見と合致しない非合理的なものであるとき、それは「悪いバイアス」としてみなされるのだと思います。特定のバイアスを持つことが、かえって組織のポテンシャルを引き出すことがあることを理解しながら、組織マネジメントにおいてうまく「思い込み」とうまく付き合い、手懐けていくことが求められるのでしょう。
安斎・ミナベのLIVE配信「組織マネジメントゼミ」始まります
ちなみに今週から、ミミ&グリが運営する学習コミュニティ「WORKSHOP DESIGN ACADEMIA(WDA)」では、安斎・ミナベによる「組織マネジメントゼミ」が始まります。ほぼ毎日”組織ファシリテーション”に関する動画コンテンツを配信しておりますが、それとは別に、毎月第2木曜日21:00-22:00の枠で、WDA会員限定でオンラインLIVE配信をします。

5月のテーマは本書のテーマに合わせて「人と組織のマネジメントバイアス」と設定し、書籍で書かれていないミナベの組織デザインのこれまでの探究と実践に基づくバイアスについてディスカッションする予定です。生配信に間に合わなくても、後から視聴可能なようにフォロー予定ですので、ぜひこの機会にWDAにご入会ください。5月限定で無料キャンペーン実施中です!
また、本書に紹介されている数々のバイアスについても、WDAでほぼ毎日配信している動画コンテンツの枠で別途踏み込んで解説する予定ですので、WDA会員の皆様はそちらも是非お楽しみにしていてください。
ミミクリデザイン &ドングリはデザインの力で創造性の土壌を耕し、組織の課題解決を実践するデザインファームです。40名の研究者、ファシリテーター、コンサルタント、デザイナーが在籍しながら、具体的な技術から思想や哲学まで含めた広い意味での方法論 (methodology) を学術的に研究しています。
学術研究を裏づけにしながら、組織をよりよくするお手伝いをさせて頂いた実例資料を無料配布しております。下記よりぜひご確認ください。